それが、子供の見た母親の最後の姿だった――
1月17日の朝、F村で農業を営む生田市之助と妻・美奈子が惨殺されて発見された。
隣人の主婦・お房によると、16日の夜に美奈子が訪問し、病気がちな当主妻のことで夫・市之助が本家に呼び出され、更に妻である自分も本家に行かなければならなくなり、熱を出している娘・雪代を預かるよう頼まれたという。
また、市之助夫婦を迎えに来た本家の使用人を自称する男は、釣鐘マントに頭巾を深く被り、自身が持つ本家の定紋が描かれた提灯の明かりからも避けるように佇んでいた。
数十年後、成人し結婚した雪代は、夫の実家の禅寺にて偶然あることに気づき、幼い頃見た光景を思い出す。
原作
作者:松本清張(1909~1992)
初出:1967年『小説新潮』「十二の紐」第三話(当時、「橙色の紐」という副題がついていた)
収録:『死の枝』新潮文庫
1960年代は「わるいやつら」「砂の器」などの代表作を発表し、ノンフィクション作品「日本の黒い霧」「昭和史発掘」の連載を抱え非常に多忙だった。
同時に、大岡昇平(「野火」「武蔵野夫人」など)との純文学論争をはじめ、評論・随筆・旅行記などで自己の見解を問い、論客としての一面を見せた。
松本清張が多趣味で造詣が深い作家である印象は、この当時の執筆活動によるものである。
松本清張は動機に重きを置く作家だが、この短編集は、更に登場人物の心裡に肉薄し、問題提起・解決の王道の流れから外れた作品が目立つ。
端的に言えば、解決させず読者に委ねる。
そして、うすら寒い不気味さを残し、読後感は良いとはいえない。
だが、それでも読ませてしまう何かがある不思議な短編集である。
余談だが、連載当時『十二の紐』のタイトルだったが、結果的に11作品に留まったためか改題し、『死の枝』になった経緯がある。
「家紋」は、度々は1990年、2002年にドラマ化されている。
ただ、1990年版は放映後、ロケ先の寺の宗派本寺から抗議を受け、再放送やビデオ化をしない合意がされたため、見ることは叶わない。
2002年版と同じ大野靖子による脚本のため、大筋は一緒と予想しているが……
市之助夫婦の内情を深く掘り下げ、非常に生々しい印象が2002年版にはある。
特に、雪代の回想はハッキリと原光景として描写されている。
また、市原悦子による朗読もされている。
昔話を語るように柔らかく、しかし淡々と事実を述べる不気味さがある。
演じ分けが凄い。
補足
モデルとなった事件

「北國新聞 明治39年(1906年)2月14日」 オカルトクロニクルより引用
実際の事件と「家紋」との違いは、以下の通り。
- 実際の事件は2月に発生(小説は1月)
- 被害者は3名(小説は2人)
- 犯人は青い毛布をかぶっていた
- 家紋入りの提灯は、実際の事件では出てこない
- 不貞行為等の関係は不明
雪の降る夜での犯行、一人ずつ呼び出したこと、子供は難を逃れたこと、迷宮入りした点は共通。
2010年に殺人罪の公訴時効が撤廃され、この事件のように時効制度による終わりはなくなった。
また、原作の冒頭一節で、F村が所属する「或る地方」は信仰心からくる共同防衛意識により、犯罪が迷宮入りするとの説明がされている。
これは、戦前の疑獄事件「帝人事件」を扱い、後に検事総長となった中野並助の著書『犯罪の通路』(中公文庫)にある「青ゲット(毛布)事件」と「一家みな殺し、寺院焼却事件」を言及した記述が影響していると思われる。
以下、引用抜粋。
刑事の手腕は聞込みの上手下手によって決まるといってもよい。ところが上手下手の問題どころか、全然聞込みのできない場所がある。私は福井へ来てから、この寺の事件のほかに、まだ二件ばかり殺人事件を迷宮に入れている。
福井では昔から大きな事件というと大方迷宮にはいっているとの聞いた。これはもちろん警察やわれわれの責任であることはいうまでもないが、一つはこの辺の信仰! 地面を歩く時にも蟻を踏み殺さないように気をつけるほど、すべて生物を殺すまいとする善心は、犯罪を知っても自分の口からは決して口外すまいとする。これが検挙に影響することは否めない。(178頁)
中野並助は、検事時代に福井に配属されていた経験もあってか、上記のように著書で述べている。
ただ、こう結論づけてしまうのは非常に危うと私は感じている。
というのも、中野の著書は「青毛布→赤毛布」「被害者3人→2人」「本家提灯が存在」など、当時の新聞(北國新聞)が報じる事実と異なる点がある。
中野も「私も実は書類や実際見聞した者について研究したのではない。ほんの風聞を聞いたに過ぎないから、誤りもあろうし、くわしくもない。」と著書で述べているため、全ての記述を前提として事件を考察することはできない。
その地域に住む人々や信仰する方へあらぬ誤解と風評被害を招くおそれがある。
そのため、この度の動画化にあたって、特定地域の名称や宗派の名を出すことを避けた。
中世の「惣」と「一揆」

「大樹寺御難戦之図 三河後風土記之内」 月岡芳年筆 明治6年(1873年)
中世日本では、惣と呼ばれる自治組織が各地で形成され、惣単位や周辺地域を巻き込んで一揆を結んだ。
動画内で述べた惣村は、百姓の惣を特にさす。
一揆は本来、揆(みち)を一つにする意味で、武装蜂起はその一例に過ぎない。
民衆が政治的要求をした場合は土一揆といい、国人(在地領主)が中心となれば国一揆という。
また、寺社も領主的な立場にあったり、惣村に対する影響力も持っていたため浄土真宗(本願寺派、高田派)、日蓮宗(法華宗)の人々による一揆もあった。
原作は、F村の宗教的結束を説明する上で、越中・加賀一向一揆を指していると思われる歴史的背景を述べている。
この浄土真宗における一向宗とは、本来の浄土宗の一派「一向宗」が踊念仏の「時宗」と混同・影響されたものが、更に浄土真宗の「本願寺」と混ざり合ったものである。
浄土真宗(本願寺、一向宗)は、比叡山延暦寺との対立で京都を追われおり宗派再興のため、村単位での布教・説法を主軸とし、結果として共感を得やすい教義の性質上、広く浸透して世俗との結びつきが強かった。
ただ、宗教の教え自体が一揆を扇動したとかではない。
当時の情勢を考えれば、一向一揆をはじめとした土一揆は、起きるべくして起こったといえる。
この当時、家督争い、将軍継嗣争い(応仁の乱、嘉吉の乱、明応の政変)で日本全土は荒れ、収束させるはずの幕府は風前の灯火となり、各地の国人(地方の在地領主)や庶民たちは「支配からの独立」「自衛」の意識を高めた。
つまり、浄土真宗を信仰する層と、自衛せざるを得なくなった層が一致した場合が一向一揆という形になる。
そして同じ信仰を持つ者同士、互いに勇気づけられたのも理由の一つと思われる。
しかも、真宗は広く信仰された多数派のため、信者であった武士階級の人間も加わり、後の時代には三河一向一揆のように内紛に発展した例もある。
越中・加賀一向一揆の詳細については割愛する。
日本史などで「90年の自治を勝ち取る」と言われ、後に上杉謙信や織田信長とも激しく対立している。
一揆の発生要因は一つではなく、情勢変化も激しいので複雑であり、思想だけで発起されたものと考えるのは適切でない。
帽子の歴史
現在、帽子は頭に被る頭巾や装身具の総称的な扱いをされている。
こうした被り物は世界的に見ても、防御・防寒・防暑の意味と、権威・職業の象徴などの意味を成していた。
日本では古墳時代の埴輪に類似するものが見られ、奈良時代には「冠」として登場し、後に「烏帽子」や「頭巾」、「笠」に発展した。
仏教においての「帽子」は「もうす」と呉音と唐音の読みをする。
元々は、勅許を得た高僧だけが被る「縹帽子(はなだもうす)」で、賜袖とも称された。
その最たる例が、天台宗開祖・最澄になる(当時は桓武天皇)。
鎌倉時代、中国(宋)の禅宗から学んだ栄西(臨済宗)や道元(曹洞宗)が正装として用い、ぼうし型の被り物を「帽子(もうす)」と呼んだ。
他宗派では、ぼうし型「帽子」を正装として用いていなかったが、威儀を高める目的で徐々に浸透した。
こうした経緯から、元は禅宗の言葉だったという説明がなされていると思われる。
また、鎌倉仏教の開祖が比叡山延暦寺(天台宗)で修行、あるいは影響された経緯から、「帽子」の文化が残ったといえるかもしれない(あくまで個人の意見です)。

観音帽子の後ろのようなもの
隙を見てスマホ(指)で描いた力作(白目)
観音帽子は臨済宗の帽子
現在のような洋風帽子は、安土桃山時代の南蛮貿易により伝来されたが、髷を結う文化のため根付かなかった。
本格的に洋風帽子が日本に浸透したのは、明治維新後になる。
断髪令(1871年)により欧化する中、洋風の帽子はフランス語の「シャッポ」で親しまれ、急速に広がった。
後に、このシャッポも「帽子」と日本風に呼ばれ、今日のような被り物の総称となったと思われる。
白提灯と家紋
白提灯は、白紙を張っただけの提灯で、葬礼用に用いられる。
一般的なのは、忌明けに初めて迎えるお盆(新盆・初盆)時のみ使用される盆提灯と思われる。
白提灯には、初めて帰る故人の霊が迷わない目印、清浄無垢の白で故人を迎えるという意味があり、主に玄関や仏壇前、地域によってはお墓に吊るし、初盆が終われば送り火と一緒にお焚き上げされた。
ただ、白提灯の扱いは宗派・地方によって違うため、以上の解説が全て正しいわけではないことをご容赦いただきたい。
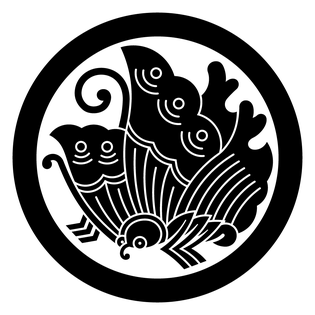
生田家の家紋として登場した家紋(丸に揚羽蝶)の揚羽蝶は、奈良時代から存在し、優美さから公家に愛用され、調度品や牛車に用いられた。
平安後期、武家の起こりとともに、武家も家紋を用いるようになる中、蝶を定紋(メインの家紋)としたのが桓武平氏(平清盛)だといわれている。
以降、戦国時代・江戸時代に平氏を称する家のほとんどが、蝶紋を用いる。
無論、図案として完成された蝶紋は人気で、他家でも見られる。
原作中では、生田家以外に揚羽蝶の家紋を使う家が周辺にないため、犯人が持つ提灯の信用性を高めた。
余談だが、家紋は全国241種(5116紋以上)存在する。
もし興味があれば、実家や好きな武将の家紋を調べると面白いかもしれない。
家紋だけでルーツは分からないが、どんな思いでそれを定紋としたのか、当時の人の考えを知るきっかけになる。
以下、ネタバレを含むので注意!
原作とスケキヨ版の違い
- 雪代視点
- 冒頭の「検事総長」の回想記カット
- 事件記録の詳細をカット
- 登場人物の来歴をカット
- 小道具(再現率ゼロの釣鐘頭巾、法衣)
- 真典が歩くシーンカット
- 義父との会話シーンカット
細かい設定や説明を省いた。
前述通り、地域や宗教の明言を避けるため。
また、被害者遺族の視点のため、真相が曖昧。

市之助と美奈子
捜査当局や表向きの評価は、夫婦仲も良好、日々の暮らしも真面目で問題なさそうな人達。
ただ、妻に疑惑があったことが発覚する。
迫られたのか、ほだされたのか、経験のない強い刺激にのめり込んだのか経緯は不明だが、子供の立場から見ればどうだろうと大差ないので、あまり深く考察しなかった。
冒頭の会話が夫婦の影を語るが、心の底から憎み合うような仲でもないというのが私の解釈である。
互いに思う所はあるが言わずにいる、良くも悪くも優しさのようなものがあると思う。
テレビドラマ版(2002年)の影響で、過去の男と市之助が対峙したことがあるような演出になっている。

また、娘への情は両人の共通し、その点に関しては互いに信頼し合う仲だったかもしれない。
(雪代がもう少し成長していたら両親のぎこちなさに違和感を覚え、察した娘の反応を巡って夫婦が争うこともなくもないが……)
市之助夫婦は、筆舌に尽くし難い。
この微妙な関係を端的に表すため、仲が悪いとは断言できない【もこう】と【かぐや】を配役した。
文庫さん改造の【かぐや】も個人的に好きだが、洗練された都会的な印象のため、今回は見送った。
雪代
両親亡き後、他分家の次男妻の実家に引き取られ、福岡で育つ。
事件渦中の人間でありながら、故郷から距離を置いていたため、外部の人間目線で考察する。
そして、幼い頃の母との思い出により、事件の核心部分に触れる。
この体験を分かち合える人間がいないことを不幸と捉えるか、事件と離れた所で自分なりに生きることが出来て幸せと考えるかは、読者によって判断が分かれるところだろうか。
「点と線」の動画化のように後日談を入れることも検討したが、良い案が浮かんだわけでもない上、私の力量ではただの蛇足になるため止めた。

配役の【さくや】は、東方ファンで考察されている来歴に基づくもの(永遠亭との関係など)。
それを考えると、【えーりん】を関係者に配役するのが自然だが、匂わせすぎなので止めた。

真典
住職。事件当時は院代(住職代理)、寺に来て3年だった。
つまり、美奈子が関係を持ったのは結婚後ということが分かる。
作中で人となりは分かりづらいが、穏やかな喋り方をし女好きの印象はない。
分家の長老が言った「女のことでよく噂があった」の女が、美奈子だけを指すか他にも女の影があったのかは定かでない。
個人的には、遊び人風に女好きというより、惚れやすく好きになったら執着するタイプだと思っている。
なお、2002年版ドラマだと、結婚前から好きだった描写があり、ストーカー気質が強調されていた。
配役に【ひじり】を抜擢した理由は僧侶だから。
東方では温和で真面目な人格者だが、来歴や設定を鑑みると影を背負っていてもおかしくはない……と言い訳しておく。
変装時の饅頭は、文庫さん改造の逆さ帽子魔理沙をパク参考にした。
いつもありがとうございます。
なお、頭巾と声を少し変えるだけでは標的にバレることなく誘き出して殺害することが可能なのだろうか。
流石に出来すぎているとも思えるが、可能性がゼロともいえない。
原作は明確ではないが戦後、田舎の街灯の数はたかが知れており、提灯の明かりだけは深い闇であること。
また、人の顔をじろじろ見て話す人は少ない上、風景に溶け込むような変装をしたり髪型を変えれば芸能人でもない限り結構気づかないものである。
それでも気づく人は気づくので何とも言えないが……
閉じた社会

前近代的な村落で醜聞や犯罪があった時、村内や渦中の中ではそれが噂になりやすいが、一歩外の世界では知られていなかったり、外部の人間には口を閉ざすということは往々にしてある。
前回「車井戸はなぜ軋る」の内からの視点に対し、「家紋」は外からの見えにくさがある。
いずれの場合にしても、外界の常識とは異なる価値観が存在し、それが時には人々を救い、逆に苦しめることもあったと思う。
インターネットの普及、交通整備がされつつある現代において、外界と遮断して内々だけの世界を作り上げることは難しく、いつかは発覚する。
だから「家紋」の事件のように、村人が黙秘を続けることも、村の慣習が優先されることも違和感を感じ、あり得ないことと一蹴され、時には警察や関係者が無能であると今は評価を受けると思う。
ただ、現代においても閉ざされた世界は存在する。
それは家庭や学校、職場だったりし、善悪で完全な区別がつけられるようなものでもない。
この「家紋」には、常識や理屈だけでは語れない闇が描かれていると思う。
あとがき
技術的なことより、どう配慮すればいいか悩んだ動画。
究極言えばこうしたデリケートな作品を扱わないことが一番、しかし腫物に触るように接するのも違うと感じた。
なので作品を取り扱う分、補足情報を編集後記で補完するよう努めた。
同時に「手に負えない物への恐怖」を表現することの難しさを痛感した。
「不倫はダメ」「閉鎖社会は害悪」ということを述べたいのではないし、「不倫はよくあること」「郷に入りては郷に従え、我慢しろ」と言いたいわけでもない、それを形に出来たか非常に不安である。
作者の松本清張が何を思って「家紋」を執筆したのか真意は分からないが、理解できない悪意や理不尽な事象と平穏な生活は隣りあわせであることを描写し切った優れた作品だと私は思う。
あと、インフルエンザで酷い目に遭ったが、なんやかんや動画編集できたので結果オーライ。
【参考】
松本清張『死の枝』新潮文庫
大橋俊夫『一遍と時宗教団』教育社
辻川達雄 『蓮如と七人の息子』誠文堂新光社
峰岸純夫、片桐昭彦『戦国武将合戦事典』吉川弘文館
遠藤武・石山彰『図説日本洋装百年史』 文化服装学院出版局刊


コメントをお書きください